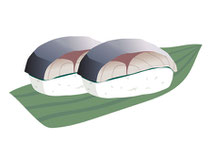
ようこそ お寺で薬膳So-Rinへ。
京都では祇園祭真最中!明日はいよいよ前祭りの鉾巡行です。
さて京都ではお祭りや行事などのハレの日には鯖寿司を食べる習慣が今でもあります。
昔は各家庭、鯖寿司を作ってご近所に配ったりしたものです。
私もお嫁に来た頃、義母が祇園祭になると鯖寿司を作っていました。
また昔は祇園祭になると京都の中京区、上京区の商家には取引先が今でいうお中元の挨拶に来る習慣があったそうで、挨拶にくる商人は鯖寿司を持参し、挨拶を受けた商家は手土産に鱧寿司を返したんだそうです。
冷凍技術のない昔、炎天下の夏、京都に魚を運ぼうとすると生命力のつよい鱧と酢でしめた塩鯖だったのでしょう。
京都ではこの祇園祭には鯖寿司と鱧寿司はかかせない料理です。
さてこの鯖と鱧、薬膳的には?気になりませんか?
辰巳洋先生の薬膳素材辞典によると
鯖は補益類(補気類)に属し、五気六味は平性で甘、働きは補肺健脾
鱧は去湿類(利水滲湿類)に属し、五気六味は寒性で甘、働きは補脾利水
お寿司ですので
ご飯は補益類(補気類)に属し、五気六味は平性で甘、働きは補中益気・健脾和胃
酢は理血類(活血化瘀類)に属し、五気六味は温性で酸味・苦味、働きは活血散瘀・消食化積
祇園祭の時期と言えば梅雨が明ける前の蒸し暑い時期です。
以前、梅雨の時期の養生でもお話しましたが、五行からみても脾、脾は湿が嫌いな臓器。梅雨の湿により胃腸が弱りやすくなる時期でもあります。
鯖の働きは健脾つまり脾を健やかにする働きがあります。
鱧の働きも補脾利水、脾を補い、余分な水分を出す働きがあります。
おまけに酢飯のご飯の働きも健脾和胃、酢も消化を助けてくれます。
この時期、本当によい料理だなぁと思います。
今年も住職と共に
疫病退散を祈りながら、鯖寿司を食べて、この夏を乗り切りたいと思います。
